はじめに
「ミニカーがテーブルに一直線にずらーっと並んでいる」
「ブロックをひたすら同じ方向に並べている」
「ぬいぐるみを順番に座らせている」
幼児を育てていると、こんな光景を目にしたことはありませんか?
親からすると「なんでわざわざ並べるの?」「毎日毎日同じことばかりしてるけど、大丈夫なの?」と心配になることもあります。
私も長男が小さい頃は、些細な行動も気になって、調べてばかりいました。
でも実はこの“並べる行動”、幼児期の大切な発達のサインなんだそう。
この記事では、幼児がモノを並べたがる理由と、それがどんな力につながっていくのかをわかりやすく解説します。
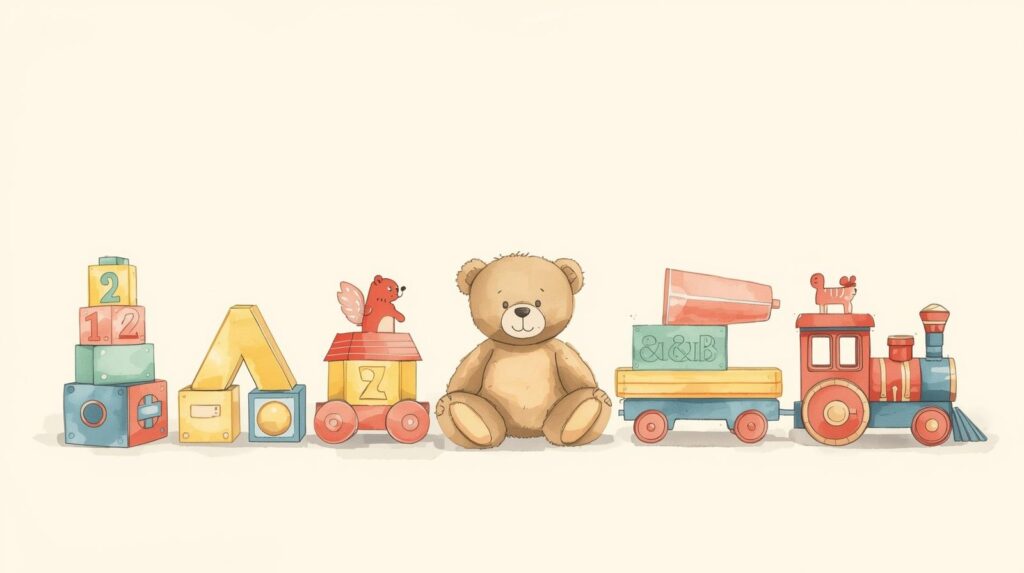
幼児がものを並べる理由とは?
「秩序感覚」を育てている
子どもは小さな科学者のように「世界はどうなっているの?」と日々観察しています。
その中で、自分なりのルールや秩序を確認したくなるんです。
たとえば、ミニカーを赤・青・黄と順番に並べて「これは一緒」「これは違う」と分類することで、色や形の違いを学んでいます。
大人にとっては単なる遊びに見えても、子どもにとっては「世界の法則を整理している」大事な実験なんですね。
安心感を得ている
同じように並べる行為は「自分の思い通りにできた!」というコントロール感にもつながります。
幼児期は、自分の気持ちも思い通りにならないし、周りの世界も予測不能なことばかり。
そんな中で、ものを並べることは「安心できる活動」なんです。
集中力と観察力のトレーニング
「ひとつずつ丁寧に並べる」という行為は、実は集中力や手先の器用さを育てる絶好の時間。
同時に「同じ・違う」を見分ける観察力も磨かれています。
並べる行動は発達のどんな段階?
0〜1歳ごろは「舐める・叩く・投げる」で物を確かめる時期。
そこから2〜3歳ごろになると、ただ遊ぶだけでなく「規則性」を意識するようになります。
2歳後半〜3歳:色や大きさを揃えて並べる
3〜4歳:役割を与えてごっこ遊びに発展
4歳以降:ルールをつくったり、友達と共有したり
つまり、並べるのは「ごっこ遊び」や「ルールのある遊び」へとつながる発達のステップなんです。
親としてどう見守ればいい?
無理に止めない
「また並べてる!」「違う遊びしたら?」と口を出したくなりますが、やめさせる必要はありません。
子どもにとっては大切な学びの時間。安全が守られているなら自由にさせてOKです。
言葉を添えて世界を広げる
「赤がいっぱいだね」
「長い列になったね」
など、一言コメントしてあげると子どもは「認められた!」と感じて、さらに発展的な遊びへ広がります。
写真に残してみる
親からすると「ただの並べ遊び」でも、後から見返すと成長の記録に。
「この頃はミニカー並べるのが好きだったんだよ」と見せてあげると、子どもも嬉しそうにしますよ。
並べる行動が長く続いたら心配?
発達の一環なので基本的には心配いりません。
ただし以下のような場合は、保健師さんや専門機関に相談してみてもよいでしょう。
• 並べる以外の遊びに全く関心を示さない
• コミュニケーションや言葉の発達が極端に遅い
• 強いこだわりで生活に支障が出ている
とはいえ、多くの場合は「その子なりの成長の一コマ」。
「今しか見られない可愛いブームなんだ」と思って見守るのがおすすめです。
まとめ
• 幼児がものを並べたがるのは「秩序感覚」を育てる大切な発達段階
• 並べることで「安心感」「集中力」「観察力」が身につく
• ごっこ遊びや社会性の発達につながっていくステップ
• 基本は見守り、必要なら言葉がけで遊びを広げてあげよう
大人にとっては単純に見える遊びでも、子どもにとっては成長に直結する「学びの時間」。
「また並べてる!」ではなく、「成長してるんだな」と思えると、毎日の子育てがちょっと楽しくなりますよ。
関連記事はこちらから↓
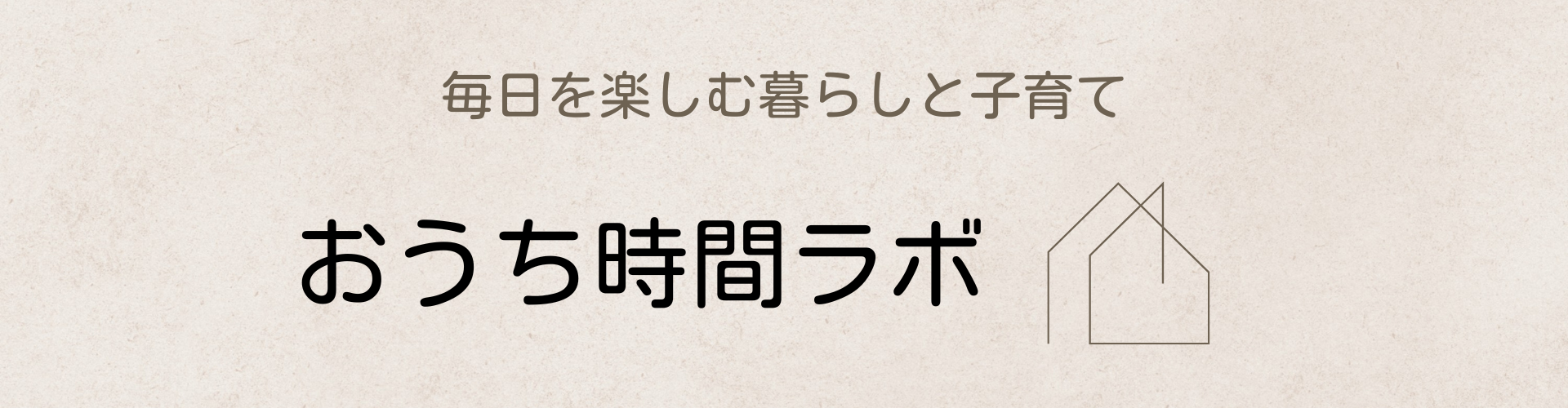
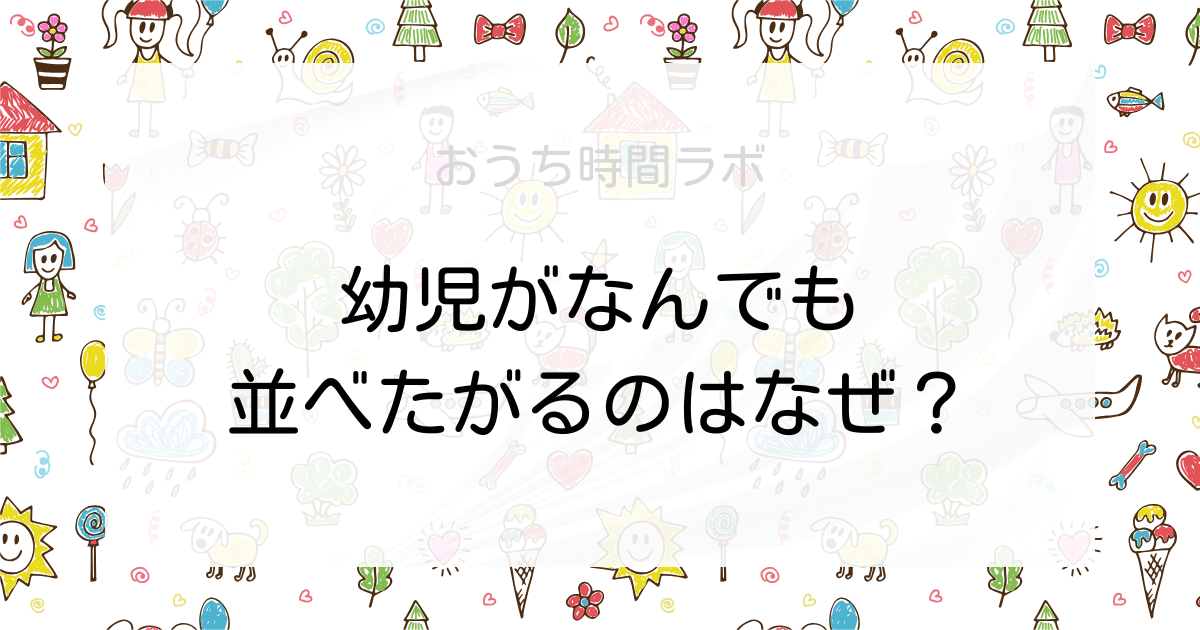
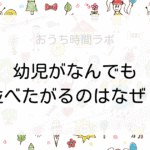
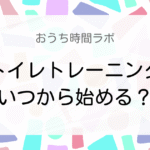
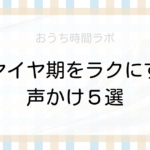
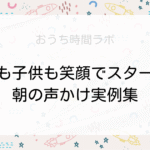
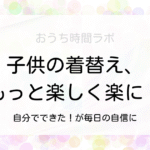
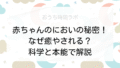
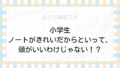
コメント